2025/07/13
フリーランスフリーランスと会社員の違いは何?メリット・デメリットや成功のコツも解説

フリーランスと会社員には働き方や収入、安定性など多くの違いがあります。本記事では両者の違いを徹底解説し、それぞれのメリット・デメリットや成功のポイント、転身事例までわかりやすく紹介。自分に合ったキャリア選択と将来設計の参考になります。
1. フリーランスと会社員の基本的な違いとは
1.1 就業形態の違い
フリーランスと会社員の最大の違いは、雇用関係の有無や働き方のスタイルにあります。会社員は特定の企業や団体と雇用契約を締結し、企業から給与や指示を受けながら働きます。一方、フリーランスは企業などに雇用されず、自らクライアントと業務委託契約を結び、案件ごとに仕事を受注します。働く場所や時間の自由度も異なり、会社員はオフィス勤務や固定時間での労働が主流ですが、フリーランスはリモートワークや自由なスケジュールを構築できることが多いです。
1.2 収入面・報酬体系の違い
会社員が固定給や賞与などを企業から支給されるのに対し、フリーランスは案件単位の報酬や時間単価での収入となります。会社員は毎月安定した給料が保証されていますが、フリーランスでは収入が不安定になる場合が多く、案件の受注数や単価によって大きく収入が変動します。その一方で、スキルや実績次第では会社員よりも高収入を目指せる可能性もあります。
1.3 働き方・仕事の自由度の違い
働く場所や時間、受ける仕事の内容など、自己裁量の範囲が広いのがフリーランスの特徴です。自分のペースでプロジェクトを進めることができ、業務選択も自由です。会社員の場合は、会社のルールや就業時間に従い、部署や上司から割り振られた仕事を遂行することが多くなります。副業やダブルワークにも制限がある企業もあり、プライベートとの両立には配慮が必要です。
1.4 社会保険や福利厚生の違い
会社員は健康保険や厚生年金、雇用保険、労災保険といった社会保険の加入が義務付けられており、会社が費用の半分を負担します。また、有給休暇や産休・育休といった福利厚生の恩恵も受けられます。フリーランスは基本的に自分で国民健康保険・国民年金に加入し、手続きや保険料負担もすべて自己責任となります。また、企業の福利厚生を利用できない点にも注意が必要です。
1.5 安定性やキャリア形成の違い
会社員は雇用の安定性が高く、長期的なキャリアパスや昇進・昇給といった社内制度を利用しながらキャリア形成が可能です。研修や教育支援なども整っているため、着実なスキルアップが期待できます。一方フリーランスは、案件の継続性やクライアントとの関係に依存しやすく、仕事量や収入が不安定になりやすいです。キャリアの選択肢が広い一方で、自己研鑽やスキルアップは自分で計画的に行う必要があり、確定申告や税金管理も求められます。
2. フリーランスのメリットとデメリット

2.1 フリーランスのメリット
2.1.1 自由な働き方・時間管理
フリーランスの最大の特徴は、自分で働く場所や時間を選べる「自由な働き方」や「柔軟な時間管理」ができる点です。通勤が不要で、家やカフェ、コワーキングスペースでも仕事が可能です。また、働く曜日や休暇も自身の裁量で決められるため、ワークライフバランスを重視したい方にとって大きな魅力となります。
2.1.2 収入アップの可能性
フリーランスは成果やスキル、営業力次第で収入の上限に縛りがなく、複数の案件を同時に進めることで高収入を目指せます。仕事を選び、自分の得意分野や高単価案件にチャレンジすることも可能です。実力や人脈があれば、会社員よりも年収が大幅に高くなる事例も見られます。
2.1.3 仕事の選択肢の多様性
フリーランスは自分の興味や得意分野を活かしたプロジェクトや取引先を選べるため、キャリアの幅が広がります。複数のクライアントと契約できるため、新しい業界や職種にも挑戦しやすく、自分に合った仕事環境をつくりやすい点も特徴です。
2.2 フリーランスのデメリット
2.2.1 収入の不安定さ
フリーランスは受注状況や景気、市場動向などに影響されやすく、毎月の収入が不安定になりがちです。仕事量が減った際や大きな案件がなくなった場合、生活の安定を欠くリスクもあります。全国健康保険協会などの公的情報も参考に、収入のリスクヘッジが必要です。
2.2.2 社会保険や年金の自己管理
会社員とは異なり、健康保険や国民年金、所得税などの社会保険・税金の手続きを自分で管理しなければなりません。扶養や出産・育児などの各種手続きも個人で行う必要があり、知識不足によるトラブルの可能性もあります。国税庁の公式情報などで正しい手続きを把握しておくことが求められます。
2.2.3 仕事探しや営業活動の負担
フリーランスは自ら営業を行い、新規案件の獲得や既存クライアントの関係維持といった仕事探しの負担が発生します。人脈作りやポートフォリオの準備、案件管理、見積もり・請求書作成など、本業以外の業務負担が増える点にも注意が必要です。
2.2.4 労働環境の自己責任
会社員と異なり、作業環境や労働時間、健康管理など、すべて自己管理になります。体調を崩しても有給がなく、仕事を休めばその分収入が減るため、安定した働き方や生活リズムを保つ工夫が不可欠です。孤独感を感じやすい場合は、積極的なコミュニケーションの場を設けるなどの対策が有効です。
3. 会社員のメリットとデメリット

3.1 会社員のメリット
3.1.1 安定した収入と雇用
会社員は企業と雇用契約を結び、毎月決まった給与を受け取ります。景気変動や案件の受注数に直接左右されることなく、安定した収入が得られるため、生活設計が立てやすいのが特徴です。また、労働基準法により、簡単に解雇されにくい制度や、雇用保険などの失業時のセーフティネットが整っています。
3.1.2 社会保険や福利厚生の充実
会社員は健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの社会保険に会社と従業員が双方で加入する形で自動的に加入します。企業によっては住宅手当、家賃補助、交通費全額支給、産休・育休、健康診断補助、慶弔見舞金など、各種福利厚生が提供されており、生活をバックアップするサポート体制が整っています。病気や育児、介護などのライフステージの変化にも対応しやすい環境です。
3.1.3 キャリアアップや教育制度
多くの企業では、新入社員研修やOJT、資格取得支援、外部セミナー受講補助といった教育制度が充実しており、会社の一員として段階的にスキルを向上させる機会が豊富に用意されています。評価や昇進基準が明確に設定されているため、目標やキャリアパスがイメージしやすい点も会社員ならではのメリットと言えるでしょう。
3.2 会社員のデメリット
3.2.1 働き方の自由度が低い
会社員は就業規則や勤務時間が定められているため、自分で仕事の量や時間、場所を選べる範囲が限られます。テレワークやフレックスタイム制度の導入が進んでいる企業も増えていますが、組織やチームで動く関係上、自分だけの都合で働き方を大きく変えることは難しいケースが多いです。
3.2.2 収入アップの限界
会社員の給与は基本給や賞与、昇給などで構成されており、一定の業績や勤続年数に応じて上がりますが、自力で大幅な収入増を目指すのは容易ではありません。また、成果主義を採用する企業でも評価は上司や会社の方針に影響されがちで、努力が必ずしも収入につながるとは限りません。
3.2.3 人間関係や職場ストレス
組織に所属する以上、上司・同僚・部下との人間関係や社内の人付き合い、チームワークが重要になります。コミュニケーションや協調性が求められるため、部署異動や転勤、人間関係のトラブル、パワハラ・セクハラといった職場ストレスが発生することもあります。自身の頑張りだけでは解決できない課題に直面する場合も少なくありません。
4. フリーランスと会社員 どちらがおすすめ?向いている人の特徴

4.1 フリーランスに向いている人の特徴
フリーランスに向いている人は、自分で計画を立てて主体的に行動できる自主性の高い人や、変化の多い環境を楽しみながら成長したいというチャレンジ精神のある人です。
また、スキルや実績に自信があり、自分の専門性を活かして自由な働き方を選びたいと考える人にも適しています。
さらに、自己管理能力や時間管理能力に優れ、クライアントとのやり取りや経理、確定申告などの事務作業も自らこなせる人が適しています。
独立心が強く、組織の枠にとらわれずに複数の案件を同時に進めたい方や、仕事の幅を広げたいという意欲のある方も、フリーランスのメリットを最大限に活かせる傾向があります。
また、自分のライフスタイルや価値観を重視し、時間や場所に縛られず仕事をしたいと考える方も、フリーランスに向いています。
参考:レバテックフリーランス「フリーランスに向いている人・向いていない人」
4.2 会社員に向いている人の特徴
会社員に向いている人は、毎月安定した収入と福利厚生が得られることや、長期的なキャリア形成を重視する安定志向の方です。
組織でのチームワークや人間関係を重視し、上司や同僚との協力やコミュニケーションを取りながら働くことが得意な方も会社員に適しています。
会社の教育制度や研修を活用してスキルアップしたい方、明確なキャリアパス・昇進制度を望む方、専門的な分野以外にも多様な業務経験を積みたいと考える方も会社員向きです。
また、社会保険や厚生年金、住宅手当・有給取得などの福利厚生が充実していることで安心して生活したいというニーズのある方は会社員のメリットを享受できます。
指示や決まった枠組みのなかで働くことが安心できると感じる方や、仕事とプライベートをきっちり分けたい方にも、会社員はおすすめです。
5. フリーランスで成功するためのポイントとコツ
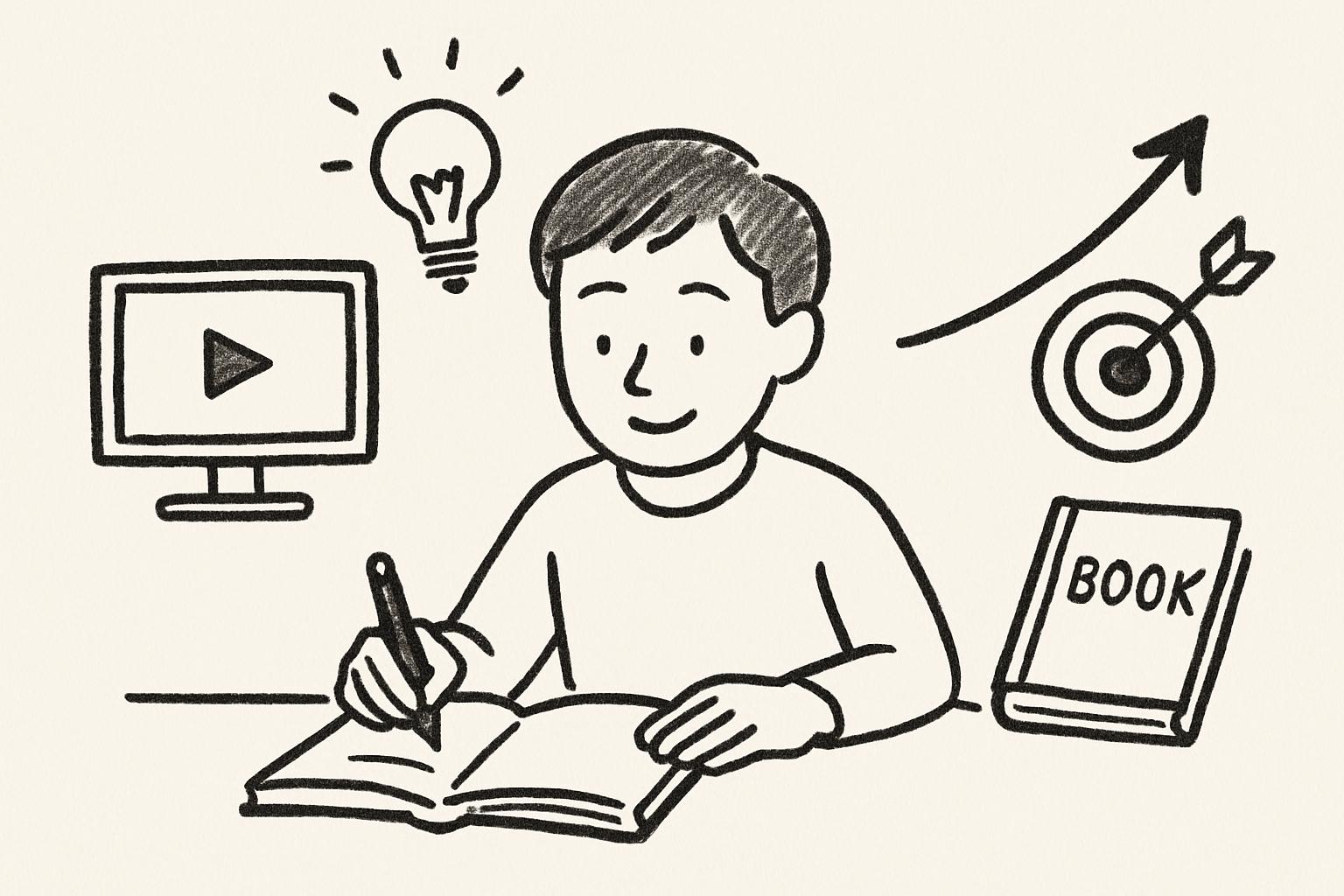
5.1 スキルアップと専門性の強化
フリーランスとして継続的に活躍するには、常に最新のスキルや知識を習得し、市場価値を高め続けることが不可欠です。ITエンジニア、デザイナー、ライターなどは、技術やトレンドの変化が速いため、オンライン講座や専門書、セミナーへの参加を通じて学び続ける姿勢が大切です。「●●のプロ」と認知される専門性を持つことで、他のフリーランスとの差別化も図れます。例えば経済産業省の公式サイトでは、IT人材やクリエイターのスキル標準も紹介されています。
5.2 営業力やセルフブランディングの重要性
フリーランスは自分自身が商品です。自身の強みや実績を明確に発信し、信頼される「ブランド力」を築く必要があります。ポートフォリオやホームページを作成し、SNSや専門プラットフォーム(Wantedly、note、Twitterなど)で活動内容を発信することが信頼獲得につながります。 また、自分から積極的に仕事を獲得するための営業力も必須です。クラウドワークス、ランサーズ、ココナラなどの国内マッチングサービスを活用した営業活動や、知人・企業へのダイレクトアプローチも欠かせません。
5.3 安定した収入を得るための複数案件管理
収入の安定化には、1社・1案件依存を避け、複数のクライアントやプロジェクトを同時に受注することがポイントです。リスク分散を図ることで、仕事が途切れるリスクや報酬遅延などのトラブルにも柔軟に対応できます。スケジュールやタスクを管理するために、GoogleカレンダーやTrello、Notionなどの業務効率化ツールの活用もおすすめです。また、請求や契約管理も徹底することでトラブル防止につながります。
5.4 確定申告・税金・社会保険の基礎知識
フリーランスは社会保険や税金の手続きを自身で行う必要があり、確定申告や経理の基本的な知識が欠かせません。毎年の所得税はもちろん、場合によっては消費税や住民税の納付も求められます。経費計上や帳簿保管などの基礎知識を身につけ、弥生会計やfreeeなどのクラウド会計ソフトを使うと、負担を軽減できます。また、将来のために国民年金基金や小規模企業共済などの活用も検討しましょう。国税庁の公式サイトで最新情報を確認して計画的に準備を進めることが安心につながります。
6. フリーランスから会社員、会社員からフリーランスへの転身事例と注意点
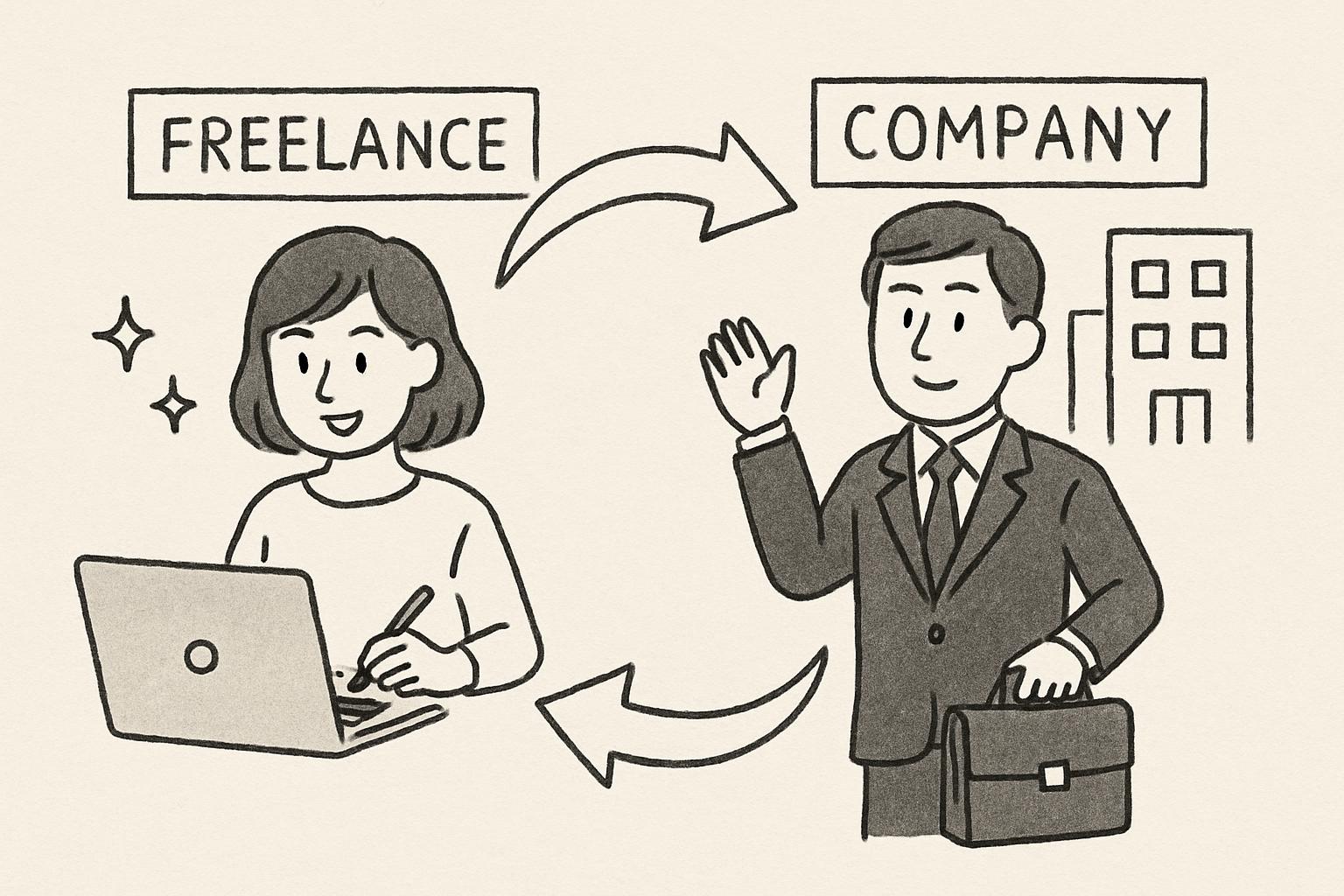
6.1 実際の転身体験談
フリーランスから会社員、または会社員からフリーランスへ転身した事例は増加傾向にあり、多様なキャリアパスが選ばれる時代になっています。例えば、Webデザイナーとしてフリーランスで活動していたAさんは、安定した収入や社会保険を求めて企業の正社員デザイナーへ転職しました。正社員となったことで業務範囲が広がり、継続的な教育や研修を受ける機会も増えたそうです。一方、会社員の営業職だったBさんは、自身のスキルを生かし独立を決意し、今ではフリーランスコンサルタントとして幅広い企業をサポートしています。Bさんは自らの裁量で働ける自由を実感している一方で、営業や請求など業務の幅も増えたことを語っています。
これらの転身事例は、キャリアとライフスタイルの見直しや将来設計に基づき、それぞれの働き方のメリット・デメリットを比較検討した上で決断されています。
6.2 転身時の注意点と準備
転身を検討する際には入念な準備が不可欠です。会社員からフリーランスになる場合、特に注意すべきポイントとして「案件獲得のための営業活動の強化」「確定申告や税金、社会保険のセルフマネジメント」「収入が不安定になる期間のための貯蓄・資金計画」が挙げられます。
またフリーランスから会社員に戻る際には、「面接時にフリーランスでの経歴やスキルをどのようにアピールするか」「会社員としての組織適応力、チームワーク能力の再構築」「就職時の条件交渉や雇用形態の確認」など、事前に確認・準備するべき点が多くあります。
いずれの場合も、実務能力だけでなくメンタル面の切り替えや情報収集、必要に応じた資格取得などが成功のカギとなります。
6.3 活用したい日本国内のサポートサービス
日本には、転身を支援する様々なサービスや制度が充実しています。会社員からフリーランスを目指す場合、ハローワークや、フリーランス協会による情報提供・セミナーの活用が効果的です。また、新しい働き方へ移行する際には「キャリアコンサルティング」や「職業訓練」「雇用保険の再就職支援制度」などの公的支援も利用できます。
フリーランスから会社員へ戻る場合には、「転職エージェント」や「オンライン求人サービス(例:doda、リクナビNEXT)」の登録がスムーズな転職活動につながります。スキルやキャリアに合わせてサポートを上手に活用することで、新たなスタートを安心して切ることができるでしょう。
7. まとめ
フリーランスと会社員には、働き方や収入、安定性、社会保険の面で大きな違いがあります。自分に合った働き方を選ぶには、それぞれのメリット・デメリットをしっかり理解し、ライフスタイルや価値観に合わせて決断することが重要です。自分の強みや将来像を明確にし、必要な準備と知識を身につけることで、どちらの道でも充実したキャリアを築くことができます。